本書で書ききれなかったこと
5つの分野に絞ったので、「廃河川跡」のページが無く、銀座の三原橋の話とか書けなかった!
代わりに、P.140の写真の所で「河川跡」の解説ページを作ろうとしたが・・・レイアウト的に変なのでボツ。
P.140の幻の原稿はこれ↓
本書では主に人工物の遺構や痕跡を紹介しているが、
「自然」を含む痕跡の分野に「河川跡」がある。
河川跡や水路跡は、埋め立てられた跡地だけが対象ではなく、
暗渠となって地下水路として残る河川や、旧河道、
橋の親柱や欄干、マンホール蓋、水門の遺構も対象となる。
渋谷区代々木5丁目には「小学唱歌・春の小川」の碑があり、川の跡を教えている。
川の流れは、河骨川→宇田川→渋谷川→古川と続いていた。
銀座の三原橋や東神田の大和橋は、地下スペースとして川の痕跡を残している。
廃河川跡ネタの出てくるページ
P.015 汚わい船の中継所跡地 (究極の下水の話?)
P.017 海岸堤防跡 (江戸川区版ベルリンの壁)
P.019 玉川上水水路橋
P.021 見沼代用水立体交差 (毛長川と見沼代用水の立体交差)
P.030 小松川閘門 (江戸川区版パナマ運河)
P.063 一之江境川→親水公園 (親水公園発祥の区:1号は古川)
P.069 玉川上水〜渋谷川
P.095 築地川跡
P.113 台場大橋跡
P.140 西井堀跡
P.143 古隅田川 (標高地形図に、荒川放水路開削前の古隅田川を記入)
P.155 葛西城址のどぶ川跡 (城の堀のなれの果て)
P.195 玉川上水新水路跡 (知られざる淀橋浄水場への玉川上水新水路)
P.197 駒沢給水所 (仮面ライダーXロケ地でもある)
P.199 調布浄水場跡
P.209 「他67B」野川旧河川跡
P.211 峰岸の水車
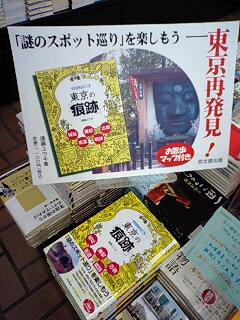
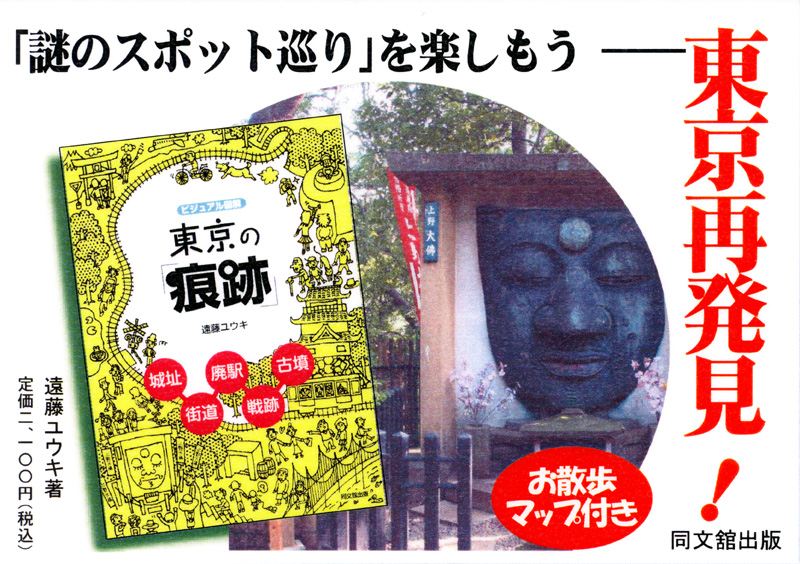
 『新廃線紀行』楽天ブックス 嵐山光三郎先生の「新廃線紀行」の中で、下河原線編道案内役、筑波鉄道写真協力しました。
『新廃線紀行』楽天ブックス 嵐山光三郎先生の「新廃線紀行」の中で、下河原線編道案内役、筑波鉄道写真協力しました。